- 不動産の売買で仲介手数料は売主と買主どちらが払う?
- 買主が決まっている不動産の仲介手数料を支払うのは?
- 不動産の仲介手数料はおかしい?仕組みを説明
不動産売買における仲介手数料は、売主と買主のどちらが支払うのか、また誰が払うのかは分かりにくく、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。さらに、仲介手数料の計算方法や支払いのルールも複雑で、取引の状況や契約内容によって変わってきます。日本では特に「買主も仲介手数料を負担する」という独自の慣習が見られます。
本記事では、不動産売買の仲介手数料にまつわる「どちらが払うのか」「仕組みや計算方法、タイミング」「買主が決まっている場合」などを詳しく解説します。さらに、手数料を抑える方法や無料サービスの裏に潜むトラブル事例、不動産会社選びのポイントまで解説していきます。
「仲介手数料はおかしい」「高額すぎる」と言われる理由や、日本特有の負担構造にも触れながら、不動産取引で損をしないための知識を解説していきます。
 小島解説員
小島解説員
買主が決まっている不動産の仲介手数料はどちらが払う?
日本の不動産業界では、「両手仲介」と呼ばれる手法があります。これは、売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることで、不動産会社がより多くの報酬を得られる仕組みです。
一方、アメリカなど諸外国では、買主から仲介手数料を受け取る慣習はなく、取引成立時に売主だけが報酬を支払うシステムが一般的です。
ここでは、「不動産の仲介手数料を売主と買主の両方が支払うのはおかしいのでは?」という疑問に対して、仕組みや日本特有の慣習、さらに買主が決まっている場合の手数料の目安まで詳しく解説します。
買主と売主のどちらが払う?
土地や建物における不動産の売買では、仲介手数料を「売主だけ」や「買主だけ」が支払うというわけではなく、基本的には売主と買主の双方が負担します。
それぞれが、自分の目的に合わせたサポートを不動産会社に依頼するためです。
売主は物件をより良い条件で売却するための手続きや価格設定のアドバイスを受け、買主は希望条件に合った物件の提案や契約のサポートを受けます。
一方で、売主と買主が同じ不動産会社を利用した場合、その会社は両方から仲介手数料を受け取ることが可能です。
これを「両手取引」と呼び、不動産会社にとっては一度の取引でより多くの報酬を得られるため、積極的に行われることがあります。
ただし、両手仲介でも必ずしも両方から満額を受け取るわけではありません。場合によっては、片方からだけ手数料をもらったり、状況に応じて半額に設定したりするケースもあります。
買主が決まっている不動産の仲介手数料は半額が妥当
知り合い同士など、すでに買主が決まっている不動産を売却する場合でも、不動産会社に仲介を依頼することがあります。
これは、契約書や重要事項説明書の作成など、売買の安全性を確保するためです。
特に住宅ローンを組む場合には、融資の審査や契約に必要な書類を宅建業者が作成するため、不動産会社の仲介が必要になります。売買後のトラブルを防ぐためにも、プロに仲介を依頼する方が安全です。
このケースでは、不動産会社が新たに買主を探す必要がないため、通常の販売活動は発生しません。そのため、一般的な仲介手数料よりも負担を抑えられる可能性があります。
中小規模の不動産会社では、こうした手間の少ない取引に対して仲介手数料を通常の半額程度に設定することもあります。
まとめると、買主が最初から決まっている不動産では、販売活動が不要な分だけ仲介手数料を抑えられます。住宅ローンを組む場合等でも必要な手続きがあるため、完全無料にはならないものの、通常の手間が少ない取引では半額にするのが妥当といえます。
もし買主が決まっている不動産売買で仲介手数料を満額請求され、値引きが難しい場合は、別の不動産会社に依頼することを検討しましょう。
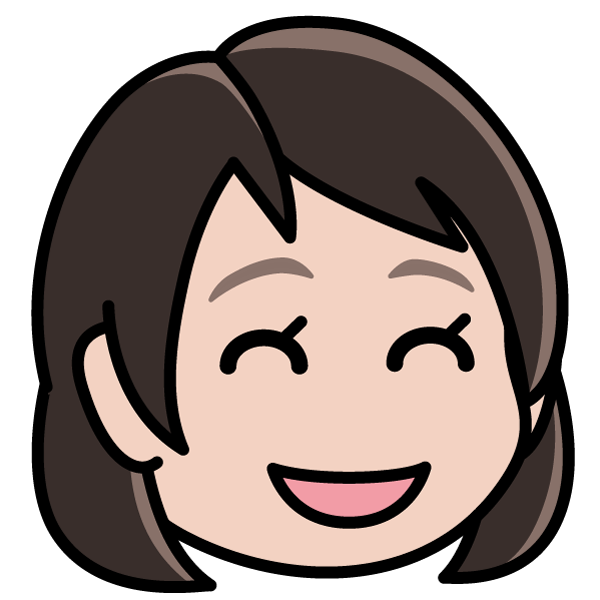 山口編集者
山口編集者
買主も不動産仲介手数料を払うのは日本だけ
不動産取引において買主は「お客さん」として位置付けられます。
しかし、日本ではその「お客さん」である買主にも仲介手数料が請求されるのです。
物件購入代金に加えて仲介手数料も発生するため、買主の負担は非常に大きくなります。
一方、アメリカやシンガポールでは、買主が不動産仲介会社のエージェントに仲介手数料を支払うことはありません。
取引が成立すると、売主が成功報酬としてエージェントに手数料を支払うシステムです。
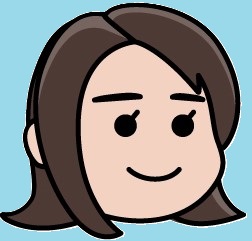 渡邊編集者
渡邊編集者
不動産の仲介手数料がおかしいと言われる理由
日本の不動産会社にとって、主な収益源は仲介手数料です。
そのため、いかに多くの手数料を得るかが各不動産会社の最大の目標となっています。
この観点から、売主・買主の両方から仲介手数料を得る「両手仲介」は、不動産会社にとって非常に利益の大きい取引です。
しかし、「少しでも高く売りたい」と考える売主と、「少しでも安く買いたい」と望む買主の希望を同時にかなえるのは難しいといえます。
 小島解説員
小島解説員
このような状況から、両手仲介を行う不動産会社は自社の利益を最大化しようとし、利益を減らすような行動はほとんどありません。
不動産売買における仲介手数料の仕組み
ここでは、家や土地など不動産取引に欠かせない仲介手数料について、わかりやすく解説します。
仲介手数料とは?成功報酬の仕組み
仲介手数料は、不動産の売買契約が成立した際に、売主と買主の双方が不動産会社に支払う成功報酬です。
つまり、物件や土地の売買取引が成立したときに発生する報酬です。
不動産会社は、売買契約を成立させるためにさまざまな営業活動を行います。
例えば、不動産ポータルサイトに広告を掲載したり、物件の内覧で購入希望者に対応したりといった活動が含まれます。
これらの活動に対する対価として、顧客から仲介手数料が支払われます。
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料の計算方法と上限
仲介手数料は、売買価格に基づいて計算される成功報酬で、日本では法律により売買価格に応じて計算方法が定められています。
具体的な計算方法は次の通りです。
売買価格が400万円以下の場合の仲介手数料
手数料は売買価格の5%です。
例:300万円の物件の場合 → 300万円 × 5% = 15万円
売買価格が400万円を超え、2,000万円以下の場合の仲介手数料
手数料は売買価格の4%に加えて2万円が加算されます。
例:1,000万円の物件の場合 → 1,000万円 × 4% + 2万円 = 42万円
売買価格が2,000万円を超える場合の仲介手数料
手数料は売買価格の3%に6万円が加算されます。
例:3,000万円の物件の場合 → 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円
この計算式を使うことで、物件購入や売却の際に必要な仲介手数料を簡単に把握することができます。
ただし、この金額は法律で定められた上限であり、実際の手数料は不動産会社の契約によって無料や値引きが行われ異なる場合があります。
また、手数料には別途消費税が加算されるため、総額を確認する際には注意が必要です。
計算方法と同じく不動産取引における仲介手数料は、法律で上限額が定められています。
これは、不動産会社が顧客に不当に高額な手数料を請求するのを防ぐためのルールです。
上限額の計算方法は以下の通りです。
売買価格が200万円以下の場合
手数料は「売買価格 × 5% + 消費税」
売買価格が200万円を超え、400万円以下の場合
手数料は「売買価格 × 4% + 消費税」
売買価格が400万円を超える場合
手数料は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」
たとえば、売買価格が3,000万円の物件の場合、仲介手数料の上限は以下のように計算されます。
3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 105.6万円
この金額は、仲介手数料の上限であり、不動産会社がこれを超える手数料を請求することは法律違反となります。
一方で、下限は法律で定められていないため、実際の手数料は交渉次第で大きく変わることがあります。
また、不動産会社が売主と買主の両方を仲介する「両手仲介」の場合、それぞれから手数料を受け取るため、最大で2倍の手数料を得ることが可能です。
一方で、消費者側としては必ずしも上限額を支払う必要はありません。
条件に応じて割引交渉を試みるのもひとつの方法です。
まずは契約前に見積もりを確認し、不明点があれば納得するまで相談することが重要です。
不動産の仲介手数料の相場【早見表つき】
不動産会社の主な収益源は、顧客から受け取る仲介手数料です。
仲介手数料の相場は、法律で定められた上限に基づき計算されます。
この上限は「物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税(400万円超えの取引の場合)」です。
例えば、3,000万円の中古マンションを成約した場合、不動産会社は仲介手数料として105.6万円を受け取ることができます。計算式は以下の通りです。
仲介手数料=3,000万円(税抜)×3%+6万円+消費税=105.6万円
両手仲介の場合、売主と買主の両方から仲介手数料を受け取るため、合計で211.2万円の収益となります。
このように、不動産会社にとって仲介手数料は非常に重要な収益源であり、両手仲介では1件の取引で2倍の手数料を得ることができます。
以下に取引価格ごとの仲介手数料を一覧にした早見表をご紹介しますので、参考にしてください。
|
取引額(売買価格)
|
仲介手数料(上限)
|
| 400万円 | 198,000円 |
| 450万円 | 214,500円 |
| 500万円 | 231,000円 |
| 550万円 | 247,500円 |
| 600万円 | 264,000円 |
| 650万円 | 280,500円 |
| 700万円 | 297,000円 |
| 750万円 | 313,500円 |
| 800万円 | 330,000円 |
| 850万円 | 346,500円 |
| 900万円 | 363,000円 |
| 950万円 | 379,500円 |
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 1,100万円 | 429,000円 |
| 1,200万円 | 462,000円 |
| 1,300万円 | 495,000円 |
| 1,400万円 | 528,000円 |
| 1,500万円 | 561,000円 |
| 1,600万円 | 594,000円 |
| 1,700万円 | 627,000円 |
| 1,800万円 | 660,000円 |
| 1,900万円 | 693,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 2,500万円 | 891,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 3,500万円 | 1,221,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 |
| 4,500万円 | 1,551,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
仲介手数料を支払うタイミング
不動産売買における仲介手数料の支払いタイミングについて解説します。
一般的に、仲介手数料の支払いは取引契約が成立した時点で行われます。
仲介手数料は取引額に基づいて計算されるため、売買価格が決まるまで具体的な金額は分からないことが多いです。
仲介手数料の支払い方法には、以下の2つのパターンがあります。
- 契約成立時、または引き渡し時に一括で支払う
- 契約成立時と引き渡し時の2回に分けて支払う
一般的には、契約成立時に仲介手数料の半額を支払い、引き渡し時に残りの半額を支払うことが多いです。
ただし、具体的な支払いタイミングや方法は不動産会社によって異なることがありますので、事前に確認することをお勧めします。
仲介手数料を無料か半額にしてもらう方法
売主・買主にとって、仲介手数料はまとまった金額になるため、負担が大きい支出です。
ここでは、仲介手数料を無料にする方法について説明します。
最初から仲介手数料無料の物件を選ぶ
まず、最初から「仲介手数料無料」の物件を選ぶという方法があります。
不動産会社に対して「仲介手数料を無料にしてください」と交渉するのは、ハードルが高い場合が多いです。
なぜなら、不動産会社の主な収益源が仲介手数料であるため、交渉されたからといって簡単に応じることは少ないからです。
そのため、買主が「仲介手数料無料」の物件を最初から選ぶのが一つの良い方法です。
不動産会社が自社販売している物件を購入する
物件を購入する際に、不動産会社が直接販売している物件を探すのも一つの良い方法です。
例えば、リノベーション済みの中古マンションを不動産会社が自社で直接販売しているケースがこれに該当します。
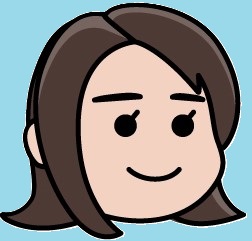 渡邊編集者
渡邊編集者
 小島解説員
小島解説員
売却の場合は不動産会社に買取を依頼する
物件を売却する際に、不動産会社に直接買取を依頼する方法もあります。
これは、不動産会社が買主となり、直接所有者から物件を購入する方式で、仲介手数料が発生しないため、コストを削減することができます。
 小島解説員
小島解説員
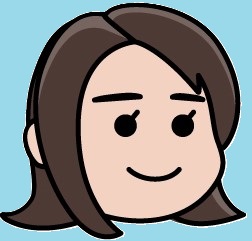 渡邊編集者
渡邊編集者
ただし、買取価格は一般的に市場価格の約70%とされているため、時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい場合は仲介を利用することをおすすめします。
不動産会社に直接値引き交渉する
不動産売買における仲介手数料は、諸費用の中でも高額な部分を占めます。
そのため、不動産会社に仲介手数料を無料にしてもらうよう交渉するのも一つの手です。
完全に無料にするのは難しいかもしれませんが、減額してもらえる可能性はあります。
特に中小規模の不動産会社の場合、両手仲介を行う際に、売主または買主のどちらか一方からのみ手数料をもらえば採算が取れるため、無料または減額を期待できる場合があります。
また、最初から「仲介手数料無料」または「不動産会社が直販している物件」を選ぶと、交渉の手間を省くことができます。
個人間での不動産売買を選ぶリスクと注意点
個人間での不動産売買は仲介手数料を初めから無料にできるメリットがあります。しかし、買主が最初から決まっている場合でも、不動産会社を介さずに契約を進めると、さまざまなリスクが生じます。
まず、重要事項説明が受けられない点が挙げられます。宅建業者は契約前に物件の状況や権利関係、法令上の制限、設備の状態などを買主に説明する義務があります。この説明はトラブル防止のため非常に重要で、個人売買ではこの手続きが省略されるため、後々の紛争につながる可能性があります。
次に、契約条件の不備によるトラブルです。売買契約では、手付金や引き渡し時期、支払い方法など細かい条件を設定する必要があります。プロの不動産会社は、過去の経験と物件情報をもとに、売主・買主双方の利益を考慮して条件を調整しますが、個人間ではこのノウハウが不足し、トラブルが発生しやすくなります。
さらに、住宅ローンを利用する場合、金融機関は仲介会社が作成した重要事項説明書や契約書を求めるケースが多く、個人間取引では融資が難しくなることがあります。また、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の取り決めも、経験不足のままでは適切に設定できないリスクがあります。
このように、買主が決まっている場合でも、個人売買では契約や手続きの透明性が確保されず、トラブルにつながる可能性が高いのです。
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料が無料になるからくりと注意点
不動産会社の主な収益源は仲介手数料のため、手数料が入らないと会社が損をするというイメージがありますが、実際には仲介手数料が無料の物件を扱っている不動産会社も存在します。
ここでは、仲介手数料が無料になる仕組みについて解説します。
売主or買主のどちらか一方からもらっている
不動産会社が手数料を無料にする場合、売主または買主のどちらか一方からのみ手数料を受け取っていることが一般的です。
両手仲介では、売主と買主の両方から手数料を受け取ることができますが、この場合、手数料の支払いが発生しない一方からもらうだけで採算が取れるため、どちらかの仲介手数料を無料にしても不利益はありません。
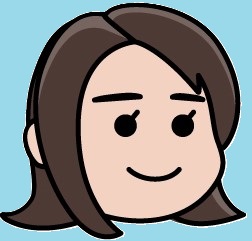 渡邊編集者
渡邊編集者
自社物件の場合は仲介手数料が発生しない
自社が販売している物件の場合、仲介手数料は発生しません。
そのため、仲介手数料をカットしたい場合は、不動産会社が直接販売している物件を選ぶのが良いでしょう。
この場合、仲介を介さずに売主(不動産会社)と買主が直接契約を結ぶため、仲介手数料はゼロ円になります。
 小島解説員
小島解説員
ネット広告で経費削減による無料化のからくり
不動産会社が注力している集客方法の一つが、不動産情報ポータルサイトに掲載するインターネット広告です。
最近の消費者は、まずインターネットで不動産情報を調べた後に不動産会社に訪れることが多いです。
インターネット広告には掲載費用が必要ですが、大手のポータルサイトに掲載することで、多くの人々の目に触れることができ、集客効果が高いのが特徴です。
さらに、営業社員の人件費やチラシ作成費を削減できるため、経費削減にもつながります。
このような企業努力により、仲介手数料を無料または減額することも可能です。
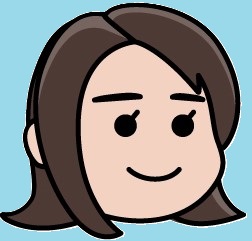 渡邊編集者
渡邊編集者
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料無料にひそむトラブル事例
仲介手数料を無料にすることは消費者にとって大きなメリットですが、一方でトラブルが発生する可能性も考慮する必要があります。
ここでは、仲介手数料を無料にすることで生じやすいトラブルについて解説します。
買主が負担する場合のリスク
売主が仲介手数料を無料にできるメリットの半面、デメリットになる可能性が考えられるのは以下の3つです。
- 不動産会社が熱心に営業活動をしてくれない
- サービスの質が落ちる
- 別の費用で請求される
ここでは、仲介手数料を無料にすることで、売主に発生しやすいトラブルについてご紹介します。
営業活動が不十分になる可能性がある
仲介手数料が高い場合、不動産会社の利益が増え、営業担当者のインセンティブ(歩合給)も増えるため、営業マンは積極的に販売活動を行います。
しかし、仲介手数料が「ゼロ」となると、会社と営業マンの利益が減少するため、物件を売るためのモチベーションが低下することがあります。
その結果、不動産会社が十分な営業活動を行わず、物件がなかなか売れない可能性があります。
サービスの質が低下する恐れがある
仲介手数料が無料になると、提供されるサービスの質が落ちることも懸念されます。
たとえば、売却に関する税務や法律の相談に対して、十分な対応が得られない場合があります。
手数料が無料である代償として、質の高いサービスを受けられないことも考えられます。
別の費用で請求されることがある
仲介手数料が無料であっても、他の名目で追加費用が請求されることがあります。
たとえば、建物状況調査(インスペクション)や事務手数料、司法書士への依頼費用など、明細が不明瞭な費用が発生することがあります。
 小島解説員
小島解説員
売主が負担するケースの落とし穴
次に買主の場合でみていきましょう。買主が仲介手数料を無料にできたことで発生しやすいトラブルは以下の3つが挙げられます。
- 他の顧客が優先される
- 売れにくい物件を紹介される
- 保証内容が手厚くない
それぞれに内容について解説します。
他の顧客が優先される可能性がある
仲介手数料を無料にすると、他の顧客、つまり手数料を上限まで支払う顧客が優先されることがあります。
不動産会社は、同じ物件を売る際に少しでも利益を上げられる顧客を「上客」と見なすためです。
そのため、気に入った物件に早々に申し出ても、なぜか他の人に先を越されることがあるかもしれません。
売れにくい物件が紹介されることがある
物件を紹介してもらえるものの、売れにくい物件ばかりを紹介される場合もあります。
たとえば、「日当たりが悪い」「周辺環境に問題がある」などの物件です。
人気のある物件は好条件・高価格で早期に売れるため、仲介手数料をしっかり支払う顧客に紹介される傾向があります。
保証内容が手厚くないことがある
購入後のアフターサービスや保証内容が不十分になることもあります。
例えば、瑕疵保証期間が短いといったケースです。
不動産会社は引き渡し後、一定期間の瑕疵保証を提供していますが、仲介手数料が無料の場合、保証内容が削られることがあります。
最初から仲介手数料無料の物件を探すのも一つの方法ですが、手数料を無料にすることで発生する可能性のあるトラブルには注意が必要です。
信頼できる不動産仲介会社の選び方
仲介手数料が無料というのは確かに魅力的ですが、無料にできた場合には潜在的なリスクも存在します。
そのため、最終的には信頼できる不動産会社に依頼することが大切です。
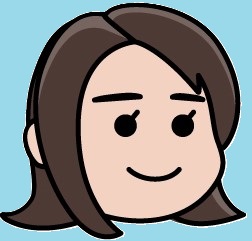 渡邊編集者
渡邊編集者
 小島解説員
小島解説員
まとめ
日本の不動産業界では、売主と買主の双方が仲介手数料を支払うのが一般的な慣習です。
そのため、仲介手数料を無料または減額にするのは難しいことが多いです。
ただし、買主があらかじめ決まっている場合などの特定の状況では、仲介手数料を減額する可能性があります。
その際は、大手よりも中小規模で信頼できる不動産会社を選ぶことで、無料や減額のメリットを活用しつつ、潜在的なトラブルを回避することができます。



