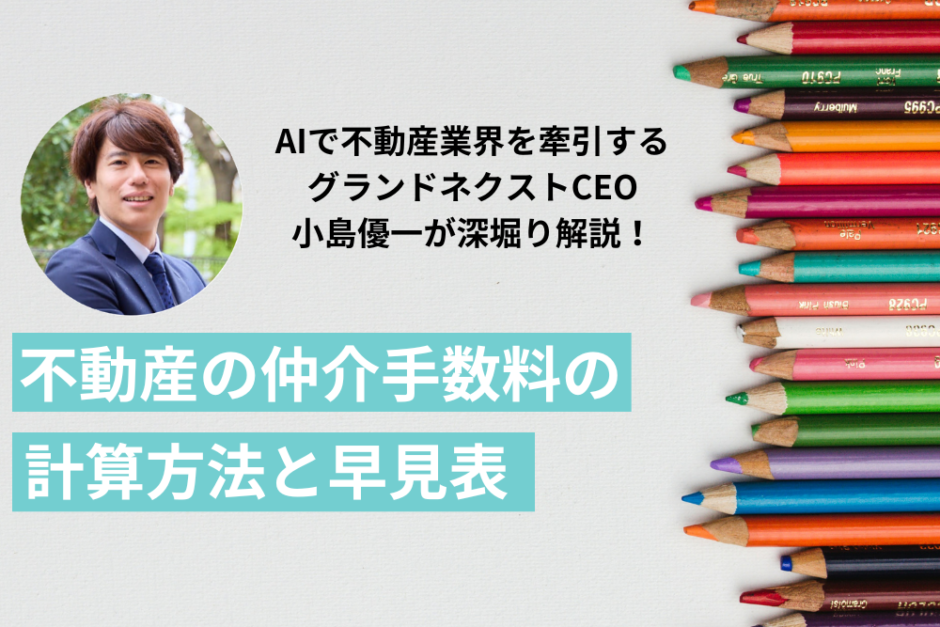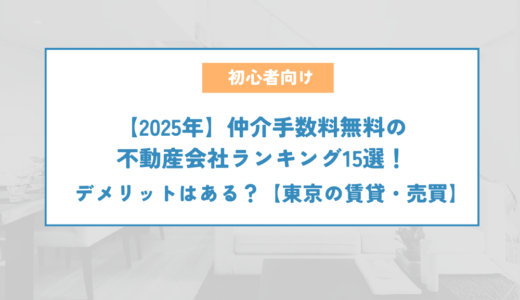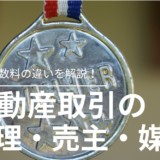- 不動産の仲介手数料の相場や計算方法を解説
- 不動産売買で仲介手数料はいつ、だれに支払えばいい?
- 不動産売買にかかる仲介手数料を安くする方法とは
不動産の売買を検討していると、「仲介手数料の相場はどれくらい?」「できるだけ手数料を抑えたい」「仲介手数料がこんなに高いのはおかしい」といった悩みが多いのではないでしょうか。
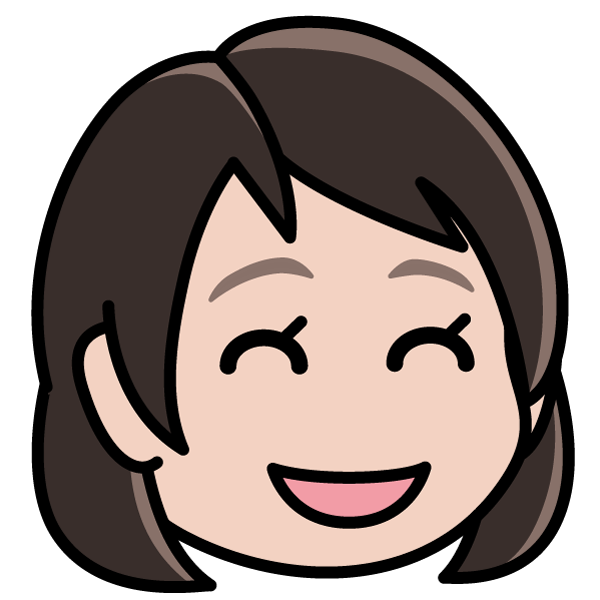 山口編集者
山口編集者
不動産取引において、仲介業者に依頼すると基本的に仲介手数料が発生します。賃貸の場合、不動産の仲介手数料の相場は家賃1ヵ月分と言われていますが、売買の場合は取引の内容によって手数料の金額が異なります。
この記事では、仲介手数料の相場、計算方法、いつ、誰が払うのかなど詳しく解説します。
 小島解説員
小島解説員
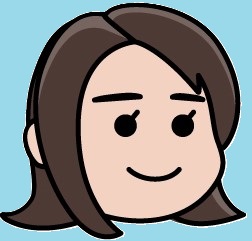 渡邊編集者
渡邊編集者
不動産売買における仲介手数料の相場

不動産の仲介手数料は、売買価格に応じて変動します。
明確な相場はありませんが、多くの不動産会社では法律で定められた上限額が実質的な相場となっています。
仲介手数料は法律で上限が決まっている
仲介手数料の上限額は、「宅地建物取引業法」で厳密に定められています。
以下の表のように、取引金額の範囲ごとに手数料の上限割合が設定されています。
「売買前に仲介手数料の相場をある程度把握しておきたい」と考える方も多いでしょう。そこで、「宅地建物取引業法」に基づく仲介手数料の上限額について、以下に説明します。
| 不動産の取引額 | 仲介手数料の上限額 |
| 取引額(売買価格)が200万円以下の金額 | 取引額の5%以内+消費税 |
| 取引額(売買価格)が200万円~400万円の金額 | 取引額の4%以内+消費税 |
| 取引額(売買価格)が400万円を超える金額 | 取引額の3%以内+消費税 |
仲介手数料の上限額は、不動産の取引額や売買価格に応じて異なります。
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料の計算式
不動産売買の仲介手数料は、不動産会社が上限の範囲内で計算しますが、取引額(売買価格)が決まっていれば、自分でも「仲介手数料の上限額」を計算することが可能です。
取引額が200万円以下の場合は「取引額の5%+消費税」という計算法で比較的簡単に計算できます。
しかし、200万円を超える取引では、200万円以下の部分と200万円を超える部分それぞれに対して計算を行う必要があります。
そのため、200万円を超える取引では計算を簡略化できる「速算法」が便利です。
- 200万円~400万円の場合:取引額(売買価格)×取引額の4%+2万円+消費税
- 400万円を超える場合:取引額(売買価格)×取引額の3%+6万円+消費税
さらに、2024年7月1日の法改正により、800万円以下の物件では売主・買主双方から受け取る仲介手数料の合計上限が最大33万円まで引き上げられました。
これにより、従来は仲介手数料が低すぎて取引が敬遠されがちだった低価格物件でも、適正な手数料で仲介を依頼できるようになっています。
800万円を超える物件については、従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限です。
仲介手数料を計算する際は、速算法を活用しつつ、法改正による上限額も考慮すると、より正確に負担額を把握できます。
仲介手数料の相場
不動産会社によっては、上限額よりも安く設定しているケースもありますが、
多くの場合、上限額いっぱいで設定しているため「3%+6万円+消費税」が実質的な仲介手数料の相場です。
たとえば以下のように計算できます。
- 2,000万円の物件 → 2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(+消費税)
- 3,000万円の物件 → 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(+消費税)
- 4,000万円の物件 → 4,000万円 × 3% + 6万円 = 126万円(+消費税)
売買金額が大きくなるほど仲介手数料も高額になりますが、どの不動産会社でも上限額の範囲内で設定されています。
不動産の仲介手数料早見表
参考までに、以下に取引額別の仲介手数料の算出例を示します。
不動産の仲介手数料早見表
| 取引額(売買価格) | 仲介手数料(上限) |
| 400万円 | 198,000円 |
| 450万円 | 214,500円 |
| 500万円 | 231,000円 |
| 550万円 | 247,500円 |
| 600万円 | 264,000円 |
| 650万円 | 280,500円 |
| 700万円 | 297,000円 |
| 750万円 | 313,500円 |
| 800万円 | 330,000円 |
| 850万円 | 346,500円 |
| 900万円 | 363,000円 |
| 950万円 | 379,500円 |
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 1,100万円 | 429,000円 |
| 1,200万円 | 462,000円 |
| 1,300万円 | 495,000円 |
| 1,400万円 | 528,000円 |
| 1,500万円 | 561,000円 |
| 1,600万円 | 594,000円 |
| 1,700万円 | 627,000円 |
| 1,800万円 | 660,000円 |
| 1,900万円 | 693,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 2,500万円 | 891,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 3,500万円 | 1,221,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 |
| 4,500万円 | 1,551,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
【例外】仲介手数料が半額や無料の場合
ここまで仲介手数料の上限や計算方法について説明しましたが、実際には仲介手数料が半額になったり、無料になるケースも存在します。
不動産会社を選ぶ際には、仲介手数料の金額を事前に確認しておくことが重要です。
 山口編集者
山口編集者
確かに、仲介手数料を無料や半額にできる中小規模の不動産会社が増えているため、最初は怪しいと感じる方もいるかもしれません。しかし、これにはきちんとした仕組みに基づいており、決して違法や不当なものではありません。初期費用を抑えるための賢い選択と言えるでしょう。
仲介手数料無料のからくりについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
 小島解説員
小島解説員
不動産売買の仲介手数料とは

不動産売買を行う際には、仲介を依頼した不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は成功報酬であり、不動産売買の契約が成立した場合に支払います。つまり、契約が成立しない限り、仲介手数料を支払う義務はありません。
ただし、すべての不動産売買で仲介手数料が発生するわけではありません。以下のような場合には、仲介手数料が不要です。
- 売主から直接不動産を購入する場合(不動産会社を介さない)
- 不動産会社が物件を直接購入する場合
上記のように、不動産会社を介さずに個人で不動産売買を行うことも可能ですが、その場合には取引に関する専門知識が必要であり、書類作成なども自分で行う必要があります。
このように個人で不動産売買を進めるには多くのハードルがあるため、実際には不動産会社に仲介を依頼するケースがほとんどです。
では、なぜ不動産会社に依頼すると仲介手数料が発生するのか、その理由について詳しく説明します。
不動産売買の仲介手数料は営業活動に対する報酬
不動産売買において、仲介手数料は不動産会社が行う営業活動に対する報酬として支払われます。
不動産会社は物件の売主や買主を見つけるために、次のような営業活動を行っています。
- 宣伝広告の作成と掲載
- 不動産のチラシ配布の手配
- 現地案内や物件見学の立ち合い
これらの営業活動を個人で行うのは簡単ではありません。「仲介手数料を払いたくないから自分で売買を進めたい」と考えても、宣伝広告の作成やチラシの配布などにはかなりの費用がかかります。
また、不動産売買に関する知識や経験が不足している場合は、不動産会社に依頼することで、手間や費用を抑えられる可能性が高くなります。
契約から引き渡しまでに必要な手続きも代行している
媒介(仲介)契約を結んだ不動産会社は、売買先を見つけるだけでなく、契約から引き渡しまでのさまざまな手続きを代行してくれます。具体的な代行手続きの例は以下の通りです。
- 契約書の作成
- 手続きにおける重要事項の説明
- 住宅ローンなどのサポート
- 引き渡しの立ち合い
- 取引する不動産の法的な調査・査定
- 不動産売買の決済
不動産会社を介さずに不動産売買を進める場合、これらの手続きも自分で行う必要があります。
 小島解説員
小島解説員
不動産売買で仲介手数料はいつ払う?

一般的に、仲介手数料の支払いタイミングは不動産売買の契約成立時です。このタイミングで、売主も買主もそれぞれ仲介会社に支払います。
仲介手数料は取引額を基に計算されるため、売買価格が決まるまでは具体的な金額を算出できません。また、仲介手数料の支払い方法には以下の2つのパターンがあります。
- 契約成立時、または引き渡し時に「一括で支払う」パターン
- 契約成立時と引き渡し時の「2回に分けて支払う」パターン
多くの場合、契約成立時に仲介手数料の半額を支払い、引き渡し時に残りの半額を支払うのが一般的です。
 小島解説員
小島解説員
不動産売買にかかる仲介手数料は安くできる?

不動産売買にかかる仲介手数料は、事前に値引きしてもらうことも可能です。
仲介手数料には上限が設けられていますが、法律で具体的な金額は定められていないため、交渉によって調整する余地があります。
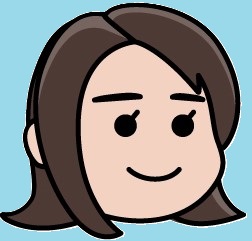 渡邊編集者
渡邊編集者
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料値引き交渉のタイミングは媒介契約の締結前
仲介手数料の値引き交渉は、不動産の媒介契約を締結する前に行うことが重要です。
媒介契約を結ぶ前は、不動産会社にとって契約の獲得が最優先となるため、値引き交渉に応じてもらいやすくなります。
仲介手数料は不動産会社の主要な収入源であるため、多くの会社が上限に近い手数料を請求する傾向があります。
しかし、中小規模の不動産会社は、大手に比べて知名度が低いため、上限に近い手数料では契約を獲得しづらいことがあります。
また、最近ではSNSやインターネットで情報発信や集客が多様化したことで、不動産売買の営業活動にかかるコストが抑えられるようになっています。
 小島解説員
小島解説員
値引き交渉を行う際には、媒介契約の締結を条件にしたり、他社の仲介手数料と比較した結果をもとに交渉すると効果的です。
仲介手数料は安ければ良いというものではない
仲介手数料の値引きを考える際に注意すべき点は、「仲介手数料が安ければ必ずしも良いわけではない」ということです。
「仲介手数料が安い」という理由だけで不動産会社を選ぶと、満足のいくサービスが受けられない可能性があります。
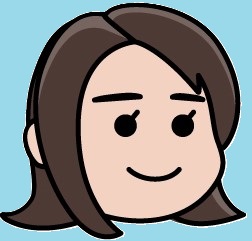 渡邊編集者
渡邊編集者
仲介手数料の値引き交渉をするメリット・デメリット
仲介手数料を値引きする最大のメリットは、売却や購入にかかる費用を抑えられることです。
「とにかく手数料を安くしたい」「新しい物件の購入を考えている」という方にとって、仲介手数料の値引きは大きな利点となります。
しかし、手数料を値引きすることで「営業活動や物件の価格交渉に十分な力を入れてもらえない可能性がある」というデメリットも存在します。
仲介手数料は不動産の営業活動に対する報酬であるため、その報酬が減少すると、宣伝に必要な広告費用なども削減されることになります。
不動産売買の仲介手数料は消費税がかかる
不動産売買の仲介手数料には消費税がかかります。
国税庁の発表によると、消費税の課税対象となる取引は以下の通りです。
- 国内で行われる取引
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の譲渡や貸付け、及びサービスの提供
※参考:国税庁「課税の対象」
不動産売買はこれらの条件に該当するため、仲介手数料には消費税が課税されます。
また、仲介手数料の消費税は取引額が大きくなるほど高額になります。
ただし、土地の売買は非課税取引とされているため、消費税はかかりません。
消費税を抑えたい場合は、仲介手数料が無料の不動産会社を選ぶか、仲介手数料そのものを値引きしてもらう方法が考えられます。
仲介手数料の勘定項目は売主か買主かで変わる
仲介手数料の勘定科目は、不動産の「売主」と「買主」によって異なります。
不動産の売却を行う「売主」の場合、仲介手数料は「支払手数料」として記録されます。一方、不動産を購入する「買主」の場合、仲介手数料は「土地」や「建物」の勘定科目に含まれます。
仲介手数料以外にかかる費用

不動産売買には仲介手数料以外にもさまざまな費用が発生します。以下の4つの諸費用について確認しておきましょう。
- 引っ越し費用
- 手付金
- 登記手続き費用
- 解体費用
引っ越し費用
現在の住宅を売却して新しい家に引っ越す際には引っ越し費用が必要です。引っ越し費用は業者や引っ越し時期によって異なるため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
また、引っ越しの繁忙期や週末を避けることで、費用を抑えられる可能性があります。
さらに、新居にすぐに引っ越せない場合は仮住まいが必要となり、その際の引っ越し費用も考慮する必要があります。
仮住まいから新居への引っ越し費用も含めて、予算をしっかりと計画することが重要です。
手付金
手付金は、不動産売買契約が成立した際に、買主が売主に対して支払う費用です。
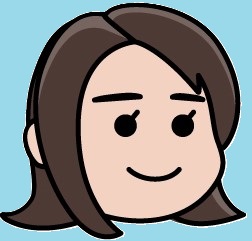 渡邊編集者
渡邊編集者
また、手付金を支払うことで、不動産売買の契約を簡単には解除できなくなります。多くの場合、手付金の支払いが売買契約の条件とされることもあります。
登記手続き費用
不動産売買には、売主と買主それぞれが負担する登記手続きが必要です。登記手続きは主に以下の2種類に分かれます。
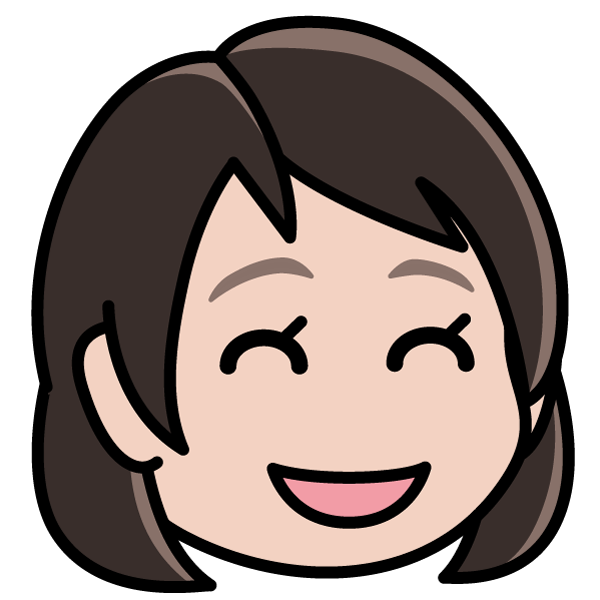 山口編集者
山口編集者
抵当権抹消登記(売主負担)
不動産を売却するためには、売主が所有する不動産に設定されている抵当権を抹消する必要があります。この手続きが「抵当権抹消登記」です。
もし住宅ローンが完済済みであれば、すでに抵当権抹消登記が行われていることが多いですが、ローンが残っている場合はこの手続きが必要です。
所有権移転登記(買い主負担)
売主から買主へと不動産の所有権を移行するための手続きが「所有権移転登記」です。
両方の登記手続きは手続きの流れが複雑で、多くの書類が必要です。そのため、司法書士に依頼するケースが一般的です。
解体費用
不動産売買で「古い家が建っている土地を購入して新たに住宅を建てたい」や「転売を目的としている」場合、解体費用が発生することがあります。
解体費用は建物の構造や立地によって異なり、一般的には100万円から300万円程度の幅があります。
 小島解説員
小島解説員
仲介手数料に関するQ&A
ここからは仲介手数料に関する番外編を質問形式でご紹介していきます。
賃貸の場合の仲介手数料の相場は?
賃貸の場合も仲介手数料は当然発生します。
賃貸の仲介手数料の相場は家賃1ヵ月分と言われており、中には半額や無料を打ち出して集客する不動産会社も増えています。
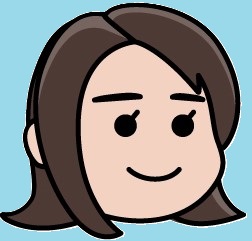 渡邊編集者
渡邊編集者
仲介手数料で法改正があった?
2024年7月1日、宅地建物取引業者の仲介手数料に関する報酬規定が改正されました。これにより、従来は400万円以下の不動産売買のみ対象だった特例措置が、800万円以下の物件まで拡大されることになりました。
これまで、売主から受け取れる仲介手数料の上限は最大19.8万円でしたが、改正後は売主・買主双方から合計で最大33万円まで受領できるようになっています。
一方、800万円を超える物件については、従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限です。
この改正は、低廉な空き家問題への一石とも言えます。日本全国に増え続ける空き家は、特に地方の低価格物件では仲介手数料が低すぎるために、不動産会社が売却依頼を受けないケースも少なくありませんでした。
価格の高い物件と低い物件で必要な手間はほぼ同じにもかかわらず、仲介手数料の低さが原因で取引が敬遠されていたのです。
今回の改正により、低価格物件でも適正な仲介手数料が見込めるため、売却を断られるケースを減らす効果が期待されます。
地方の空き家流通活性化を後押しする意図が感じられる改革と言えるでしょう。
まとめ
仲介手数料は、不動産会社が行う営業活動やその他の必要な手続きへの報酬として支払います。一般的には、不動産売買の契約成立時に支払われることが多く、契約が成立しない限り仲介手数料は発生しません。
ただし、売主から直接不動産を購入する場合や、不動産会社が不動産を直接購入する場合には、仲介手数料は発生しないことがあります。
仲介手数料には明確な相場は設定されていませんが、「宅地建物取引業法」により上限額が設けられています。また、仲介手数料の値引き交渉も可能です。
媒介契約を締結した後では値引き交渉が難しくなるため、媒介契約の締結前に値引き交渉を行うことがおすすめです。
ぜひ本記事の情報を参考にして、納得のいく不動産売買を進めてください。